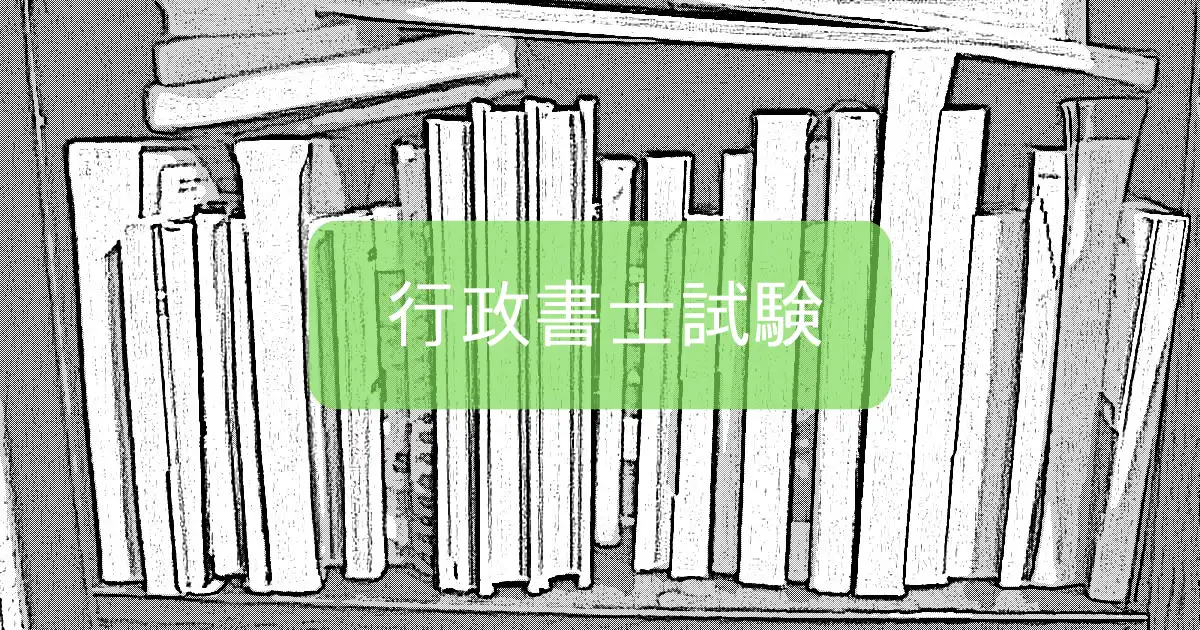つい最近令和3年度の行政書士試験の合格発表がありました。私は受験回数は4回か5回か忘れましたが、平成29年の試験で合格しました。今回は行政書士の試験を受験しようと思ったきっかけや合格までの道のりなどを紹介したいと思います。
私は初学者向けの基礎的な講座は受講していないのですが、模試や答練、無料ガイダンスなどは受講したことがあります。一応独学と言えるのかもしれませんが、予備校などのyoutube動画や書籍の参考書や問題集だけを利用して完全に一人で勉強するという独学ではないので、その点をご理解いただいたうえでお読みください。
30代で勉強開始
若い時から法律の仕事に興味はありました。ただ、弁護士以外の資格を知りませんでしたし、調べようともしませんでした。ある時、弁護士以外の法律系の資格ってどんなのがあるのかに興味を持ち、調べたことがありました。そこでときに見つけたのが司法書士と行政書士でした。
そこから、その仕事と試験について知ろうと思い、情報を集め始めました。
図書館や古本屋で司法書士や行政書士の仕事に関する本を読み、仕事についてある程度理解しました。また、試験の概要も書かれていたので読むと、受験科目は重なる科目もあると知り、どちらも受験しようと決めました。
資格を持っていれば開業という選択肢も持てるし、どこかに就職するにしても役に立つと思ったので、この時すでに30代半ばくらいでしたが、勉強を始めることに抵抗はありませんでした。
私の勉強方法と注意点
基本テキスト
基本となるテキストですが、多くの種類が出ていたと思いますが、何冊もあっても訳が分からなくなりそうだったので、読んでみてこれなら自分で読めそうだというものを選んで買いました。
記述用テキスト
記述用は上記とは別で買いました。選んだポイントですが、問題が多くても多分やらないだろうなと思ったので、基本を押さえていてなるべくシンプルなものを選びました。
注意点
私はどちらも中古で買いました。中古は予算的に安く済むのでありがたいのですが、ここに大きな注意点があります。
それはズバリ、”古い”ということです。
行政書士試験では法律問題が出ます。法律は新しい条文ができたり、逆に今までの条文がなくなったりすることがあります。そのため、古いテキストだと新しい条文に関して書かれていなかったり、逆に今では必要でない内容が記載されていることがあるので注意が必要です。独学で勉強していてこの点はネットで調べるなどしてかなり気を付けていました。
もし中古のテキストを購入しようと考えているのであれば、この点は注意を払う必要があります。
これから一から勉強を始めようとしているのなら、中古ではなく試験年度に合わせたテキストを利用する事をおすすめします。
インプットとアウトプット
勉強に関しては、基本は購入したテキストでのインプットでした。アウトプットはネットで行政書士試験向けのサイトを探して、そこにある問題を解いたりしていました。過去問集を買ったかどうかは覚えていませんが、公式ホームページに試験問題はあったので、それを解いたりしていました。とにかくよくネットを利用していたのは覚えています。今思えばですが、過去問集や問題集を買って手元に置き、数をこなすことをした方がよかったように思います。
模試
行政書士試験に関していろいろな予備校がありますが模試を開催しているところがあります。
本試験の受験回数は4回か5回ですが、そのうち直近の2回くらいは試験前に模試を受けるようにしていました。理由は二つあります。
・実力を測る
・試験に慣れる
実力を測る
予備校などに通学していなかったので、自分の実力を知る機会がなかなかありませんでした。ある程度問題が解けるようになっても、それが試験を受けるにあたって十分な力なのか、受験者全体の中でどれくらいの位置なのか、など自分では把握できませんでした。
そこで、模試を利用して自分の点数を知るようにしていました。また、私が受けた模試には、大まかにですがコメントがついていたのでそれを参考に勉強していました。
ちなみに書かれていたコメントですが、基本的な力が不足しているということでした。その後の勉強は基本事項に重点を置くようにしました。
試験に慣れる
勉強するときはそれぞれの科目ごとに勉強しましたが、試験は一度に全科目を受験し、しかも時間制限のある中で解かないといけないので、ある程度対策が必要だと考えていました。具体的な対策としては、試験の流れの把握と時間配分の仕方です。
試験の流れや解き方
問題用紙が配られどの位置の問題用紙を置くとか、試験が開始したらどの問題から解くかなどです。あらかじめある程度決めておいてルーティーンのようにしておけばそれだけで緊張は少し和らぐだろうと考えていたので、そういったことを試してみるために模試を利用しました。
時間配分
行政書士試験は、択一問題と記述問題があります。記述は文字を書く作業があるので、多めに時間をとる必要があります。どのくらいにするかはその人で異なると思いますが、自分はこのくらい必要ではないかと時間を決めて、模試はその時間で解くようにしていました。
試験当日
ここからは合格した平成29年度の試験の話です。
模試も受けたし、時間配分も決めたし、あとは今までやってきたことをやるだけという気持ちで臨みました。
本試験で分からない箇所はもちろんありました。特に覚えているのは記述の行政法でした。どうしようか一瞬迷いましたが、そこは潔く諦め、民法の2問をしっかりやろうと、試験中に割り切ったことを今でもよく覚えています。
試験後、帰ってきて自己採点をしました。試験中は手ごたえはわかりませんでしたが、ネットで解答速報を見ているときに、ひょっとしたら合格ラインに届いているかもと少し期待を持ちました。ただ、期待が大きいと不合格だった時のショックも大きいので、それ以降はあまり考えないようにしていました。
結果
通知が送られてきて、また例年通りだろうな、なんて思って開けてみたら、合格区分に「合格」と書いてありました。この時は本当に嬉しかったです。
合格した年、何が合格につながったのかを自分なりに考えてみました。それは「基本的な内容の理解」だと思います。平成27年度と平成29年度を比べてみると以下になります。
平成27年(2015年)択一は150点、記述は10点。合計160点で不合格。
平成29年(2017年)択一は160点、記述は34点。合計194点で合格。
択一はほぼ同じくらいですが、記述が34点だったので私の場合はこれが決め手になりました。
記述は、27年度以前で全く書けなかったこともありましたが、合格した年は、基本的な問題だったため比較的解きやすく書きやすかったです。行政法は捨ててしまったのでわかりませんが、少なくとも民法の2問は基本的な内容でした。合格率はこの年は15%くらいで高い年でした。
記述に限らず基本的な内容の理解は大事なんだと改めて実感しました。基本が理解できていたからこそ書くことができたのだと思います。
試験はいろいろな問題が出題されるので、過去問や基本さえやっておけばいいというわけではないと思います。
あくまで私の場合ですが、基本的な内容が自分の弱点だったのでそこをカバーしたことでいい結果につながったのではないかと思います。模試のコメントがとても役に立ちました。
最後に
私の場合は、独学で始めて、途中から模試などを利用するという形をとりました。数年かかりましたが合格はしました。独学であればすぐに勉強を始められます。費用もテキスト代と模試代程度で確かにあまりかかりません。今は試験対策アプリもあるので取り組みやすくなっているかもしれません。
ですが、自分で勉強のペースを考える必要が出てきたり、必要な情報を自分で探したりという手間がかかったりします。おそらく予備校に通ったり、通信制の講座で勉強したりした方が効率よく勉強できるのではないかと思います。学校に通えば周りに同じような受験生もいるので、気持ちを引き締めてより頑張ることもできるかもしれません。
- テキストは試験年度に合わせて
- 模試を利用
- 試験当日はやってきたことを出すだけ
- 基本的な内容の理解は大事